| 〔掲載順〕 | 〔掲載日〕 | 〔卒業年〕 | 〔卒業回数〕 | 〔 氏 名 〕 | 〔タ イ ト ル 〕 |
|---|
| 第 2 回 | 2009.6.1 | S27年 | 山城高4回 | 澤 美枝 | 炭点前 ・懐石編 |
|---|
 |
「茶会の客振り」 (NO.1) 席入り編 (2009.5.1付 掲載) (NO.2) 炭点前・懐石編 (2009.6.1付 掲載) (NO.3) 後座編 (2009.7.1付 掲載) (NO.4) 表千家流のお茶のいただき方 (2009.8.1付 掲載) |
|---|
| 茶会の客振り | 炭点前 ・懐石編 |
| 解説 澤 美枝 | |
| 茶は日々の暮らしです。特別な事ではありません。客を招いてのおもてなしです。 先日 ある会社の営業の方が茶事に参加してくださった時の感想が 私の茶事が“お客様が 満足して下さるように神経を使い気配りしておもてなしする。 そして、もう こりごり と思わせないで また是非来たいと想わせるこのお茶の接客の知恵”が自分たち営業マンの 理想に通じる!! 何とか横を向いておられるお客様を我が社の方にも関心を向けて頂く営 業活動に役立つ! と感銘され、商工会のリーダーが遠方からバスで仲間を連れてこられて 再び茶事に参加されました。 そう言う意味で、あらゆる暮らしの中で 何かのお役に立て ば と懲りずに続きをかきます。 ●炭点前 席入り 挨拶につづいて * 炉の時期(立冬〜立夏)は炭を直します。そして懐石の間に炭がおきて 釜の湯が わき 部屋も暖まる。 * 風炉(ふろ)の時期は 暑いのにカッカと炭がおこりシュンシュン湯が沸くのを避け、懐石 の後で炭点前をする。 炭を直すのは亭主であり 客の心得は特にないが、 |
|
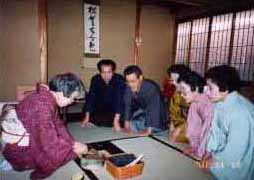 |
亭主が点前の途中で最初に羽根で炉の 周りを掃けば ○客は炉の時期なら炉の周りに近づい て 炉の中の灰をまき整え、炭(胴炭 丸ぎっちょう 割ぎっちょう 管炭 |
割管炭 白い枝炭 添炭)を適宜 つがれるのを拝見して添炭まで拝見して 自席に戻る。 香をたいて香合の蓋を閉めれば、 ○ 正客は香合拝見を願い出て 連客一 同丁寧に拝見して、また出されたと ころ近くへ返す。 |
 |
|
| ● お膳 ・飯椀 完全に出来上がったのでなく、間もなく炊きあがる位の柔らかい 飯、ほんの一口 ・汁椀 一口の飯にみあう位の量の汁 ・向付け ・箸 |
 |
 |
|
| 懐石膳が運ばれる。 ○ 客は一足にじり進んで・・亭主に少しでも運ぶ距離を短く。本来は亭主一人で客 全員のお膳を運び 半東がちょろちょろ茶室へはでないもの。 ここまで書いて思い出したが 近頃 茶会に行っても肝心の亭主がお茶の点前 をせずに社中にやらせて 自分は半東をする。半東は 東、即ち主人の半分の立 場と言う事まで知らない茶人が多い・・膳を受け取り 膳を持ったまま礼。 膳を膝前に一度置いて にじり進んだ分だけ 下がり、次客に「お先に」の礼をして 膳を自分の膝前まで引き寄せる。 *膳の出る前に 座布団など運ばれる事あり。その時も少しまえに進み出て受け取って 前に置いて 自席にさがり、膳の時同様 「お先に」と次客に声を掛け、 座布団を 自分の膝下へ スルリと引き込む。 下座まで膳が運ばれると 茶道口で、 「どうぞ お取り上げください」の亭主の言葉で、 ○ 客一同 「お相伴いたします」。 ○ 右の汁碗 左の飯椀の蓋を右手、左手で同時に開けて左の飯椀の方が大きい蓋なの で、右の汁碗の蓋を上にして 蓋同士かぶせあって 膳の右畳の上に置く。 ○ 一口の飯とそれにみあう汁が入っているので頂く。飯はいつも少々残しておく。 ● 酒と 盃が人数分、盃台に乗せられて運ばれてくる。 ○ 盃(盃台ごと)を次客との間に置き「お先に」と盃を1枚取って亭主の酒を受ける。 ○ のんだ盃は 膳の上の向付けを少し左に寄せて 向付けの右側に置く。 ○ 酒が出たら初めて向付け(主に魚の刺身)に手を付ける。 ○ 飯と一汁一菜(向付け)が最初の膳に乗ってますが、 ●煮物椀 ここで二菜目の煮物椀が出る。膳の右向こう角に置かれるので ○ 自分の膳の右 畳の上まで引き込む。 (後から運ばれたものは 盃以外膳の上に置かないで 膳の右畳の上に取り込む) ○ 煮物椀を頂く時は、しゃにむに箸を付けて食べないで ・ まず 蓋を取って 中の美しい盛りつけの様子を見る。 ・ ほんのりのだしの香りをかぐ。 ・ 汁をまず一口。 ・ それから 具に箸を付けて頂く。 (ここまで書きながら ワインを頂く時と同じだなあ!) ●飯器が出てくる。(飯の入ったお櫃) ○ 「どうぞ お任せを」といって わざわざお給仕していただかず自分で飯をよそう。 ●汁替え 最初一口にみあうみそ汁だったのでおかわりを勧める。 ○ 汁椀は少し懐紙で清め(あまりゴシゴシしない。亭主側は台所に持っていった客の 汁椀は 一度 湯できれいに洗って改めて みそ汁 具を入れるから)蓋をして 亭主の差し出す給仕盆に乗せる。 ○ 亭主が汁替えに客の椀を持ってさがったら 飯器(この時点の飯は完全に炊きあが った状態の飯)から飯を自分で好みの分量だけ飯椀につぐ。 |
 【煮物椀】 |
 【飯椀 汁椀の蓋 ・盃・などの配置・・ 一汁三菜(他の采)出揃った図】 |
|
| ●焼き物(魚) これが三菜目 ● 酒 ● 飯器(この時の飯は完全に蒸らせた状態) 注1 ここまでが 飯の段 ● 亭主は「水屋でお相伴しますので どうぞごゆっくり」の声をかけて 襖をしめる。 ○このとき正客は「どうぞ お持ちだしで ご一緒にどうぞ」と声をかける事になっている が本当は“それどころでない”水屋でまだまだ次の用意が必要なので 此はマナーの流れで すが 少し変です。亭主は辞退して 水屋でいただきます。 注2 一汁三菜と申しましたが近年は ●炊き合わせ ●和え物 その他もろもろのお菜を 出すことがある。 本来はこのお菜は 酒の肴と言う事でこの後の酒の段でだすものですが 酒を呑まない女性が多く客になる様になったので先の飯の段で出すようになって終った。 ○ 客の方は出された料理を取り回して頂く。お菜は椀の蓋などに取る。 ・飯椀に少し飯を残して お菜は全部頂く。頂き終わったら ・飯椀 汁椀の蓋をして ・煮物椀は膳の向こう側真ん中 畳の上に返しておく。 ○ お詰めの客は ・酒器 ・飯器 ・焼き物皿 ・その他鉢類すべて茶道口にかえす。 ● その頃を見計らって亭主もお相伴を水屋で済ませ 襖を開け、返されてる食器をひく。 ● 吸い物椀(後吸い とも 箸洗いとも言う)を出す。 (注) 飯の時間は終わり これから酒席となり 気分も改め 箸をこの吸い物で 洗う と言う意味。 ● 此の吸い物椀を出すときに同時に 煮物椀を引いて帰る。 茶道口で「どうぞ お吸い上げください」 ○ 吸い物椀を膳の右畳の上に引き込む。呑み終わったら蓋の露をそっと拭いておく。 ●八寸 (これから酒の席) 亭主が八寸( 酒の肴 なまぐさ類 精進類等盛り合わせ)を持ち出し客の前に座り酒をつぐ |
 【八寸 例1】 (なまぐさ 精進) |
 【八寸 例1】 (特殊な盛りつけ・吹き寄せ) |
|
 |
○客は・酒を受ける ・膳の向こうに出された八寸 を取り上げて 八寸の盛り合わ せを拝見。亭主の方へ八寸を向 けて返しておく。 ● 亭主が青竹の箸で 客の吸い物椀の 蓋に八寸の酒の肴(なまぐさ類)を 取って 客に手渡す。 下座まで終わったら また 正客の前に もどって肴(精進類など)を取って差し 上げ、 「お流れを頂戴したい」正客の盃でお酒 を頂きたい旨を伝えて |
| ○正客は盃台に自分の盃を少し清めてのせ酒を亭主につぐ。 ● 亭主 お流れの酒をいただき また 盃を盃台に乗せて返して酒を正客につぐ。 これを連客最後まで繰り返す。 また 正客の盃で 亭主〜連客〜亭主〜連客と交互にお流れを頂く事もある。 千鳥の盃などと言っている。 どんどん酒、酒の肴が出てきて 酒宴が盛り上がって良い。 ○そろそろ頃を見計らって正客は「お湯を頂きたい」と酒が充分の旨を亭主に伝える。 ○客は 吸い物椀をかるく清めて 膳の向こう真ん中 畳の上に返しておく ● ・湯斗 (釜のそこのお焦げを 湯で煮て薄い塩味のお湯) ・香の物を差し出し 吸い物椀を引いて帰り 襖を閉める ○正客は香の物を取って次客へ回し 湯斗の湯の子を 湯の子掬いで湯と一緒に掬って 飯椀に少し残してある飯の上にそそぎ、湯斗の次口から湯を 飯椀、汁椀両方にそそぎ 香の物で椀をすすぐようにきれいに 頂く。(禅の作法に通じる) 全部いただき終わったら ・詰めの客は 湯斗器 香の物鉢など茶道口へかえす。 ○箸を落とす。落ち着いたら 正客にあわせて 箸を少し音のするように膳の上に落とす。 これは「ごちそうさまでした。いただきました」の合図であって、決して「1・2 の3」 などと子供みたいな合図しない。静かに客は正客の動作に会わす。 ● 箸の音で亭主が襖をあけて 主 客 挨拶。 ● 正客より順に 膳を引く ○ 最初と同様 少し膳を前に出して 自分も少し進み出て 亭主に膳を手渡す。 ● 菓子(濃茶のため)の入った 縁高、五段重を正客の前に差し出す。 ● 亭主は茶道口に下がり 「濃茶が出来るように道具も改めるので 一度露路の腰掛けにお出まし願いたい」旨 伝える。手洗いの案内などもする。 ○正客は、用意が出来たときは、わざわざ最初のように迎え付けに露路まで出て頂かなくて も「どうぞ 鳴り物で知らせてくださって結構です」と声を掛けておく。 ● 襖閉める。蹲踞に今一度 水を足す。あたりの飛び石、植え込みにも清々しく水打ち。 ○菓子を取る。 正客は五段重の下から取る。下座まで取り 一同一緒に菓子を頂く。 ・ お詰めの客は五段重を茶道口にかえす。 |
 |
 |
|
| ○客は今一度席中の床の掛け物、道具など拝見して草履を履いて露路に出る。 ほろ酔い気分でもあり、露路に清々しく水打ちされた植え込みの緑、そして胸の奥まで 深呼吸した空気が美味しい。気持ちの緊張も一休み。そして此から席入りして 本日の メインイベント“濃茶席”の新たな静寂、緊張の席へ。 ほろ酔い気分を引きずらない。 気持ちの転換。これも演出、趣向の一つ。この流れはうまく出来ていますね! ●亭主もこの間に 衣服も礼服・・男子なら黒紋付き、女子も紋付きに改める。 本日お招きしたのは “粗茶一服差し上げたく”、 この濃茶を差し上げる為である。 ○手洗いなど済ませ 腰掛けの円座に腰掛け静かに鳴り物の音での案内を待つ。 |
| 頁のTOP |