| 【 会員の随筆 「空の散歩」 】 | −NO.11− (最終回) |
| 〔回数〕 | 〔掲載日〕 | 〔 路 線 名 〕 | 〔 航 路 事 情 〕 | 〔 訪 問 都 市 〕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 11 回 | 2009.8.1 | オセアニア路線 | 東京 → シドニー | シドニー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オセアニア路線 |
|---|
| ◎ 航路事情 シドニー 〜 成田 |
|---|
| オーストラリア・シドニーは新婚カップルをはじめ一般の日本人観光旅客にとっても人気のスポットであり、往路、復路とも満席に近い乗客が乗り込んでくる。 日本とは僅か1時間早くなるだけの時差しかなく、食べ物は日本人に馴染みやすく気候も一年を通じて温暖で日本のように酷暑、酷寒はない。 筆者は、この路線が太平洋戦争の中頃から敗戦に至るまでの主たる戦場であり、多くの同胞の血を流した跡地であるだけに、鎮魂の気持ちを込めてその上空を飛ぶ機会を秘かに待っていた。筆者は昔、国民学校4、5年生頃から級友と共に零戦パイロットに憧れ、毎日の朝刊の紙面を飾っていた華々しい戦果に、釘付けにされた年代である。それだけに敗戦まで珊瑚海海戦をはじめ、ソロモン諸島ガダルカナル島やニューギニア島での死闘、ガム島、サイパン島、テニアン島、そして硫黄島での玉砕とあたかもこの路線上を南から北へ敗退していったわが日本軍の冷厳なる敗戦の現実を直視するに忍びなかった。 |
 |
午前9時、シドニー空港を飛び立ったあと夕刻午後5時30分頃成田空港に着くまで巡航中は、太陽は沈む事がなく、雲さえなければ陽光輝く渺茫とした海原に、幾多の戦跡を残す島嶼が眺められる。 オーストラリア大陸を離れると先ず真下にグレート・バリア・リーフ、右手にあの大海戦のあった珊瑚海が見渡せる。更にほぼ1時間半飛ぶと、ニューギニア南東部オーエン・スタンリー山脈の南に、豪軍基地のあるポート・モレスビーが白砂の中に見え隠れする。 「1942年(昭和17年)5月、ポート・モレスビー攻略に端を発したニューギニア戦は、敗戦まで続いた凄惨な戦闘となった。深いジャングルと疾病と飢餓、至る所で米豪軍に包囲された日本軍は、人間の極限まで戦って敗れ去った。戦死15万7千人、東部から西端まで追い詰められつつ、日本軍は戦った。」(決定版昭和史―破局への道) 42年7月、第51師団が上陸作戦を実施したが失敗した「ラエ」とおぼしき所が眼下に見える。 しかし、ニューギニア島上空は赤道低圧帯の影響で一般に雲が多く、地上物標が生憎見えないことが多い。 離陸約5時間後、トラック諸島が右方にケシ粒のように小さく見えてくる。 トラック島は米軍が「日本の真珠湾」と呼んだぐらい、戦艦武蔵をはじめとする連合艦隊が在泊していた。それが一戦も交えず脱出、島は壊滅した。 更に1時間飛ぶとマリアナ諸島が視野に入ってくる。 1944年6月、サイパン島陸海軍守備隊3万余は米軍6万を超える火力の前に壊滅、島の北端マッピ山頂に追い詰められた女性の一群は、50メートルの断崖から身を投げた。7月、ガム島陸海軍2万の守備隊も米軍の猛攻の前には、なす術もなく玉砕した。 上空からは殆ど平坦な島に見えるが、丘陵の洞窟陣地を利用したゲリラ戦に米軍は手をやいたという。 東京へは後2時間弱というところに硫黄島が忽然と姿をみせる。 45年3月、日米両軍が死闘を繰り返した本大戦中、最大の激戦の地であり、指揮官栗林中将率いる2万余の将兵が戦死し、日本軍は完膚なきまで敗退した。茶褐色の土を露出したすり鉢山を真下に見るころ、無念に散っていった将兵 |
 シドニー近郊 |
| ◎ シドニーの街 |
| 成田空港を午後8時頃離陸、翌朝6時半(現地時間)頃シド ニー空港に着陸。市街フィツロイ・ガーデンにあるアラメン噴 水傍のNホテルで朝食をとったあと2〜3時間仮眠する。 午後、オリンピック会場にもなったラシュカッターベイへ、途 中多くの大きな紫色の花弁をつけた樹木ジャカランダを眺め ながら、傍のベイ・パークを散策したあとヨットハーバーまで 足を伸ばすのがここでの習慣になっている。 深く入り込んだ静かな入江に係留してある数十隻の豪華な ヨットを見て回ったり、帰りは船具ショップに立ち寄り、ボート 用具を見て歩くのも面白い。 |
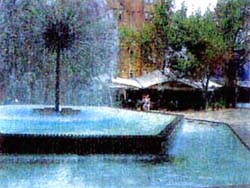 エル・アラメインの噴水 |
|
 シドニーの町 |
 ベイ・パーク |
オーストラリアの歴史を辿ると、1770年、英国人キャプテ ン・クックがシドニー湾に上陸したのが最初であり、1785年 、英国王室が領有を宣言、土地をニューサウスウェルズと名 ずけた。3年後、初代総督アーサー・フィリップ率いる船団が 流刑囚、海兵隊とその家族1200人を上陸させ、白人によ る流刑植民地オーストラリア建設が始まった。19世紀の中 頃、ゴールド・ラッシュが始まり、人口も増え、1901年1月 、白豪主義による「オーストラリア連邦」が発足した。 |
| しかし彼らの故郷はあくまで英国であり、有色人種は白人より劣等であるという偏見を1970年頃 まで持ちつづけた。有色人種特にアジア人に対する差別政策を撤廃したのはその直後からである。 現在約400万人がシドニー市に住み、シドニーはオーストラリア連邦最大の都市であるが首都キャン ベラはその南に位置している。 或る晴れた日、王立植物園、ハイド・パークを抜け、ダーリング・ハーバー内のオーストラリア国立 海事博物館へ散策を兼ねながら訪れたことがある。 |
| 館内の一角に捕獲され、引き上げられた日本海軍の特殊潜 航艇一隻が展示してあった。 それは、1942年5月、太平洋戦争下にオーストラリアを攻撃 すべく3隻の潜航艇がシドニー湾に進入、魚雷2本のみを積ん だ2人乗りの小さな潜航艇の一隻は防潜網に絡まりシドニー港 入口で自爆、一隻は爆雷攻撃をうけた結果自爆の道を選んだ。 残りの一隻は魚雷を発射、軍艦一隻を沈没させ、その後脱出に 成功したが行方はわからなかった。 その4日後、オーストラリア海軍は、自爆した2隻を海底より 引き上げ、乗員4名に海軍葬を行い丁重に葬った。 これら2隻の潜航艇を一隻に復元したのがここに展示された ものである。艇内は整頓され、自決の際使用したであろうピス トル一丁が、小机の上におかれていた。 当初潜航艇は、キャンベラの戦争記念館に保存されていたと 思われる。 戦時下敵国日本軍人に対するこのような行為は、国内でも かなりの批判があったが、シドニー地区海軍司令官、モアヘッ ド・グールドは、4名を次のように讃え弔った。 「これらの日本海軍軍人によって示された勇気は、誰もが認 めるべきであり、一様に讃えるべきである。このような鉄の 棺桶に乗って死地に赴くには最高度の勇気がいる。 これら勇士の犠牲的精神のその千分の一でも持って、祖国に 捧げるオーストラリア人が果たして何人いるであろう」。 |
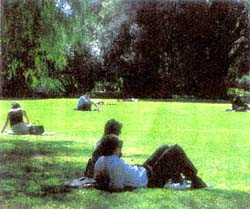 ハイド・パーク 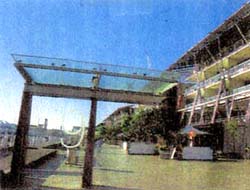 ダーリング・ハーバー |
|
| これには後日談がある。 その後4人の遺骨は、日英の戦時交換船によって帰国したが23年後の1965年、戦争記念館 館長夫妻が、遺族の松尾敬宇中佐の母のもとへ訪れ、墓前で母に、「オーストラリア全国民がご 令息の勇気を尊敬しています」と語った。 それから3年後、83歳の気丈夫な母は、独りシドニー湾の絶壁に立ち、春の陽光が明るく降り注ぐ 狭い湾口を見つめて、 「よくもこんな狭い所を抜けて襲撃したものです。母は心から褒めてあげます」 と頬を涙で濡らしながら呟いた。 その後首都キャンベラに飛び、戦争記念館長から遺品の まで 肌身はなさず身につけていた実直さに哀しみがこみあげ、館長の手をとるやその場で、泣き崩れた。 享年24歳。 筆者は白豪主義のオーストラリア人の中にも武勇を尊ぶ懐の深い軍人がいたことに驚くとともに、 24歳のわが子を褒めた母親の気概に、昔の日本女性の気骨を見る思いがした。 |
| * 千人針 1枚の布に千人の女性が赤糸で一針づつさして縫玉を作り、武運と無事を祈って 出征兵士に贈ったもの。日清、日露戦争の頃に始まったという。(千人結びともいう) (完) |
京三中・山城高校同窓の皆様方へ 11回にわたる長期間、私の拙い紀行文に目を通していただき有難うございました。今回を以って 終了します。このたびこの随筆が全国文芸同人会コスモス文学の会第13回シニア文学新人賞ノン フィクション部門で佳作に選ばれたことを同会より伝えてきました。 文学老人の見果てぬ夢が少し叶えられた気持ちです。 最後になりましたが、ホームページ掲載にご協力いただいた方々に厚く御礼を申し上げます。 山城高4回卒 吉田 和夫 |
 【無断転載、掲載を禁ずる】 |
| 頁のTOP |
| 〔空の散歩〕目次 | ||||
| 第10回 〔ロンドン〕へ |